|
住吉区山之内・平野区長原などの発掘調査で、今から10万年前のナウマンゾウの足跡が化石で発見されています。3万年前には、人間も住むようになっていました。そのころは今よりも気温がずっと低い「氷期」で、海面も今より100メートル以上低く、大阪湾も陸地でした。日本とユーラシア大陸も陸続きだったので、ゾウも人間も大陸から歩いてわたってきたものと考えられています。
人びとは石でつくった道具(石器)でけものをしとめたり、木の実などを採って食料にしていました。平野区の長原遺跡では、石器をつくっていた工房の跡がみつかっており、石器に適したサヌカイトと呼ばれる石を、大阪府と奈良県の境にある二上山からわざわざとってきて使っていたことがわかっています。
こちら(大阪市立自然史博物館)をあわせてごらんください。
人びとは石でつくった道具(石器)でけものをしとめたり、木の実などを採って食料にしていました。平野区の長原遺跡では、石器をつくっていた工房の跡がみつかっており、石器に適したサヌカイトと呼ばれる石を、大阪府と奈良県の境にある二上山からわざわざとってきて使っていたことがわかっています。
こちら(大阪市立自然史博物館)をあわせてごらんください。

 人が住みはじめたころ
人が住みはじめたころ 縄文時代・弥生時代のくらし
縄文時代・弥生時代のくらし 古墳時代の大型倉庫
古墳時代の大型倉庫 古代の都―難波宮―
古代の都―難波宮― 中世・近世の大坂
中世・近世の大坂 近代・現代の大阪
近代・現代の大阪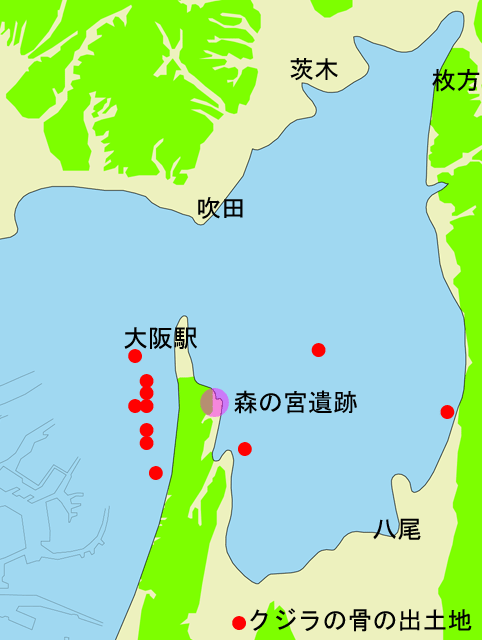 わが国ではじめて土器が使われたのは、今から1万年あまりもむかしのことです。その土器を縄文土器とよんでいます。このころ気候が温暖化して海面が上昇し、6000から7000年前には、左の図のように生駒山のふもとまで海になりました。そこではいろいろな魚にまじって、クジラも泳いでいました。
わが国ではじめて土器が使われたのは、今から1万年あまりもむかしのことです。その土器を縄文土器とよんでいます。このころ気候が温暖化して海面が上昇し、6000から7000年前には、左の図のように生駒山のふもとまで海になりました。そこではいろいろな魚にまじって、クジラも泳いでいました。
 弥生時代に続く時代は、古墳がさかんにつくられたことから古墳時代とよびます。現在の奈良県と大阪府には、特に大きな古墳がつくられており、ひじょうに力のつよいクニができていたことがわかります。それが大和朝廷(大和王権)で、中心人物を「大王」(おおきみ)といいました。後の天皇です。
弥生時代に続く時代は、古墳がさかんにつくられたことから古墳時代とよびます。現在の奈良県と大阪府には、特に大きな古墳がつくられており、ひじょうに力のつよいクニができていたことがわかります。それが大和朝廷(大和王権)で、中心人物を「大王」(おおきみ)といいました。後の天皇です。
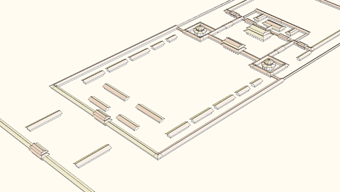 大阪城のすこし南の
大阪城のすこし南の Adobe Reader ダウンロードページ
Adobe Reader ダウンロードページ 
