|
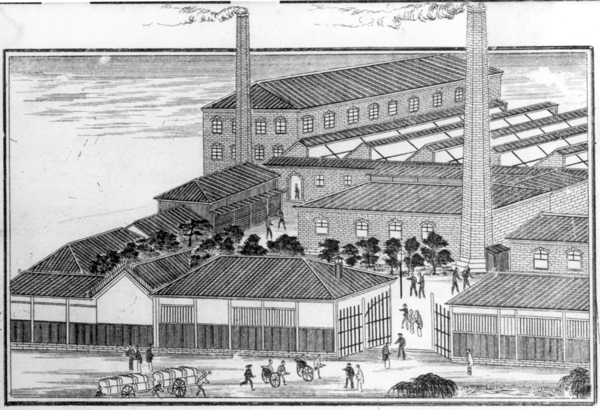 1868(慶応4)年7月、大阪は海外貿易のために開港しましたが、開港にともなって外国の人びとのために川口に居留地(きょりゅうち)がつくられました。居留地には舗装道路や西洋風の家がつくられました。付近には牛肉屋、パン屋、洋服屋など、当時の人びとにとってはたいへん珍しい西洋の文化があふれ、大阪の文明開化をうながしました。
1868(慶応4)年7月、大阪は海外貿易のために開港しましたが、開港にともなって外国の人びとのために川口に居留地(きょりゅうち)がつくられました。居留地には舗装道路や西洋風の家がつくられました。付近には牛肉屋、パン屋、洋服屋など、当時の人びとにとってはたいへん珍しい西洋の文化があふれ、大阪の文明開化をうながしました。
大名がなくなったことで、大阪の繁栄のもとであった蔵屋敷が廃止されるなど、明治維新は大阪にとって不利なことも多く、まちは火が消えたようにさびしくなりました。一方明治政府は硬貨や大砲の工場を大阪に設けたので、そこから近代的な工業の知識や技術が、大阪に根づいていきました。1890年代ごろから、繊維工業がさかんになると、大阪は工業都市として再生し、人口も増え、市街地が広がっていきました。
「大阪市」が生まれたのは、1889年(明治22)のことです。当時の市の広さは江戸時代の大阪三郷とおおむね同じで、面積は15.2平方キロメートルと、今の広さの14分の1。人口は47万人あまりでした。1897年(明治30)の市域拡張で55.6平方キロメートルになり、 1925年(大正14)の第2次市域拡張で181.6平方キロメートルになりました。そして1955年(昭和30)の隣接6か町村編入や、港の埋め立てにより、現在は222.11平方キロメートルになっています。
→市域の広がりについてはこちら(大阪市)をごらんください

 原始・古代の「おおさか」
原始・古代の「おおさか」 中世・近世の大坂
中世・近世の大坂 近代大阪の夜明け
近代大阪の夜明け 大阪港の改修
大阪港の改修 「のりもの」のうつりかわり
「のりもの」のうつりかわり 「大大阪」の時代
「大大阪」の時代 戦争中のくらしと大空襲
戦争中のくらしと大空襲 焼けあとから復興へ
焼けあとから復興へ 世界の国から ―万国博―
世界の国から ―万国博―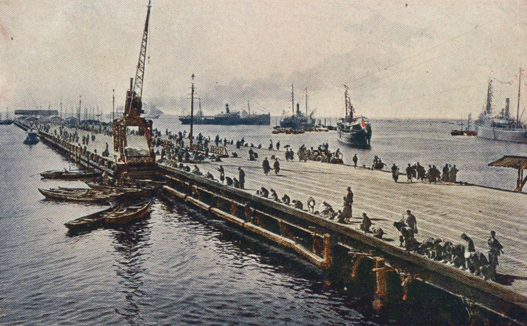 このころまで、大阪には大型の汽船が入れる港がなく、そのことが町の発展をさまたげていました。大阪の発展のためには立派な港が必要だというたくさんの市民の熱意により、新しい港がつくられることになったのは、日清戦争が終わったあとの1897年(明治30)のことです。安治川口と木津川口から沖に向かって総延長10キロメートルの2本の防波堤をつくり、その内側を9メートルの深さにするもので、人工的に築いた港という意味で、「築港(ちっこう)」と呼ばれました。
このころまで、大阪には大型の汽船が入れる港がなく、そのことが町の発展をさまたげていました。大阪の発展のためには立派な港が必要だというたくさんの市民の熱意により、新しい港がつくられることになったのは、日清戦争が終わったあとの1897年(明治30)のことです。安治川口と木津川口から沖に向かって総延長10キロメートルの2本の防波堤をつくり、その内側を9メートルの深さにするもので、人工的に築いた港という意味で、「築港(ちっこう)」と呼ばれました。

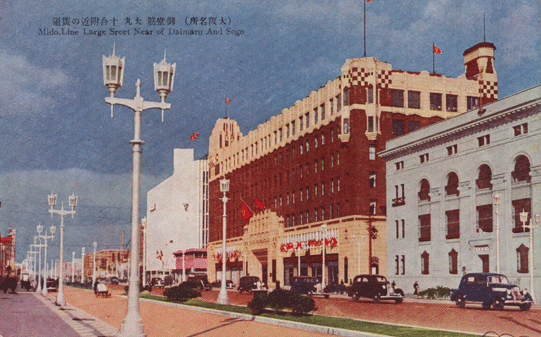
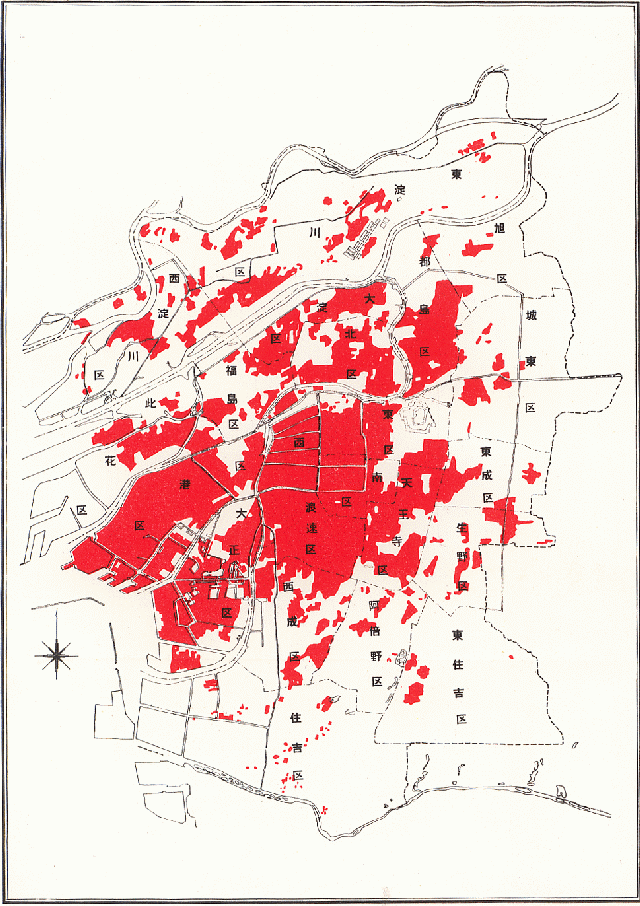
 人が集まりましたが、外国からもたくさんの人がやってきて、博覧会を見物するとともに日本の人びとと友好の輪をひろげました。
人が集まりましたが、外国からもたくさんの人がやってきて、博覧会を見物するとともに日本の人びとと友好の輪をひろげました。
 Adobe Reader ダウンロードページ
Adobe Reader ダウンロードページ 
